【クライアントアラート】エネルギー転換におけるマルチ・コントラクト型契約構造 ― 洋上風力と蓄電池(BESS)の事例研究
クライアントアラート:
エネルギー転換におけるマルチ・コントラクト型契約構造
― 洋上風力と蓄電池(BESS)の事例研究
1. エグゼクティブサマリー
洋上風力タービンや蓄電池システムといった高度で専門性の高い技術に依拠するプロジェクトは、単一のEPCコントラクターが全体責任を負う構造ではない構造で組成されることが多くあります。このようなマルチ・コントラクト型の契約アレンジメントにおいては、発注者・施工業者・サプライヤー・インテグレーターのいずれもがリスク増大に直面します。業務範囲の不整合、責任の重複、複雑なインターフェースにより、プロジェクト全体に遅延・紛争・コスト増加のリスクが波及するのです。
洋上風力や電池エネルギー貯蔵システム(BESS)では、この動態がよく表れています。洋上風力はタービン価格の高騰、施工船不足、海洋工事の困難化に加え、米国の政策上の不確実性や日本の制度改革に直面しています。一方でBESSは、規模は比較的小さいものの、鉱物価格の変動、技術進化の速さ、少数のグローバルOEMへの依存といった特徴的なリスクを有しています。
いずれの分野でも、OEMが担う範囲は限定的であり、全体責任を引き受ける当事者は存在しません。そのため複数の契約を並行して管理せざるを得ず、義務の空白や重複が生じます。結果として、発注者・施工業者・サプライヤーの誰もが、実行リスク、遅延の連鎖、業務範囲・性能・責任をめぐる紛争にさらされることになります。
重要な示唆は、洋上風力やBESSにおけるマルチ・コントラクト型の契約構造は、リスクの積極的な配分、義務の早期の整理、そして複数当事者間の強力な調整がなければ成立し得ないという点です。
事例 1: 洋上風力
洋上風力開発は、タービン価格の急騰、施工船不足、海上物流のボトルネックによって大きな制約を受けています。日本では、国内タービンOEMが存在しないこと、大容量モデルをめぐる国際競争、円安の進行といった課題が重なり、すでに計画の遅延や中止が発生しています。
米国では、リースや許認可に関する連邦政策の不透明さが投資家の不確実性を増幅させています。対照的に日本では、リース条件の明確化、許認可手続の簡素化、FIT・FIPといったインセンティブの拡充が進められており、安定性と投資家からの信頼の向上が図られています。
契約面では、タービンサプライヤーは機器供給を担うものの、海洋工事リスクを回避するため、発注者はプラント工事、基礎、施工船、系統連系、ローカル工事などを個別契約で手当てする必要があります。こうしたマルチ・コントラクト型構造は調整を困難にし、一部の範囲で遅延が発生するとプロジェクト全体に波及します。
保証や性能義務も整合しておらず、保証期間や条件が異なるため、発注者が穴埋めリスクを負う可能性が高まります。さらに、開発初期に締結される固定価格契約は、コスト上昇に直面すると不採算となりやすく、EPC一括契約では認められないコスト転嫁条項により、発注者が追加コストを負担する場合も少なくありません。
また、契約解除条項は不可抗力や倒産などに限定されることが多く、インフレや為替変動といったマクロ経済ショックに対しては救済策が乏しい状況です。施工業者にとっても、OEM保証と自らの義務の不整合により、合理的にコントロール不能なリスクを負うことになり得ます。
事例 2:電池エネルギー貯蔵システム(BESS)
.BESSプロジェクトは、リチウム・ニッケル・コバルト価格の変動や技術進化のスピードにコスト構造が大きく影響されます。さらに市場は少数のグローバルOEMに依存しており、供給集中リスクが顕著です。これらのリスクは洋上風力とは異なるものの、資金調達や実行面で同様に複雑性をもたらします。
洋上風力と同様に、BESSでもフルEPCラップは稀です。OEMはセル供給と保証を担いますが、プロジェクト全体責任は負わず、システムインテグレーション、PCS、EMS、BOPは別々の事業者が担当します。土木や系統連系も独立した契約となるため、保証の不整合や調整リスク、性能義務をめぐる紛争が生じやすい構造です。
マルチ・コントラクト型契約構造は、保証の不整合、調整リスク、そして性能義務をめぐる紛争を生じさせる。施工業者にとっては、これが自らの業務範囲や管理の及ばないリスクへのさらなる露出につながり得る。洋上風力の場合と同様に、固定価格の供給契約やサービス契約は変動する投入コストと両立させるのが難しく、退出条項も限定的である。
また、BESS特有のリスクとして、性能保証が劣化曲線、往復効率、稼働率などに紐づけられますが、その定義はOEM・インテグレーター・オフテイカー間で統一されておらず、発注者にとって救済が不明確となるケースがあります。加えて、劣化や火災リスクに対する保険商品は依然として限定的で、投資家の不安要因となっています。
政策と協働
日本では、洋上風力とBESS双方で政策基盤の強化が進んでいます。促進区域制度によるリース条件の明確化、承認手続の簡素化、インセンティブ制度の強化などが代表例です。
また、協働の芽も出てきています。洋上風力では経産省がSiemens Gamesa、GE VernovaといったOEMやTDK、日本製鉄など国内企業との連携枠組みを整備し、強靭なサプライチェーンの構築を目指しています。BESS市場では、Bison BrothersとEngelhart CTPによるMoUのような提携が、協調的な開発や財務ストラクチャリングの新たな傾向を示しています。包括的なアライアンス契約はまだ端緒にとどまっているが、こうした取り組みはリスク管理に対するより統合的なアプローチへの移行を示唆しています。
一方米国では、新規リースに対する連邦モラトリアムや規制の反転措置が投資意欲を削ぎ、契約の進化どころかプロジェクトの成立性そのものが課題となっています。
実務的示唆
洋上風力とBESSは、それぞれ異なる要因に起因しつつも、マルチ・コントラクト型契約構造が重大なリスクを生むことを示しています。
- OEM、インテグレーター、施工業者間の調整が必要となり、遅延が連鎖しやすい
- 保証・性能義務の不整合により、保証範囲の空白が発生し得る
- 開発初期に締結された固定価格契約は、設備コスト上昇や原材料インフレに直面すると不採算化する
- 契約解除条項が限定的で、発注者がマクロ経済ショックの影響を直接負担する場合が多い
すべての関与者は、リスク配分の明確化、保証の整合、調整メカニズムの早期導入に努める必要があります。特に施工業者は、複数当事者間の早期協議に参加し、契約義務が現実的な実行リスクを反映するよう働きかけることが求められます。
今後のセミナーご案内:マルチ・コントラクト型契約構造におけるリスク配分とマネジメント
当事務所では、洋上風力とBESSの事例研究を踏まえ、「マルチ・コントラクト型契約構造におけるリスク配分とマネジメント」をテーマとするセミナーを開催します。
セミナーでは以下のトピックを取り上げます:
- エネルギー市場におけるマルチ・コントラクト型契約紛争の実例
- 開発事業者・施工業者・OEM・金融機関におけるリスク配分とマネジメント戦略
- バンカビリティを確保したプロジェクト遂行を可能にする市場・政策フレームワークの進化
エネルギー開発事業者、施工業者、OEM、金融機関、政策担当者の皆さまに特に有益な内容となる予定です。詳細やご登録については、追ってご案内いたします
ご質問がある方はseminar@tkilaw.comまでご連絡ください。
(Written by: ホジョン・ジュン, マイケル・リンチ, 竹内 悠介)
※本記事の内容は、一般的な情報提供であり、具体的な法的又は税務アドバイスではありません。
ご質問などございましたら、ご遠慮なくご連絡ください。

東京国際法律事務所
E-mail: hojung.jun@tkilaw.com

東京国際法律事務所
E-mail: michael.lynch@tkilaw.com
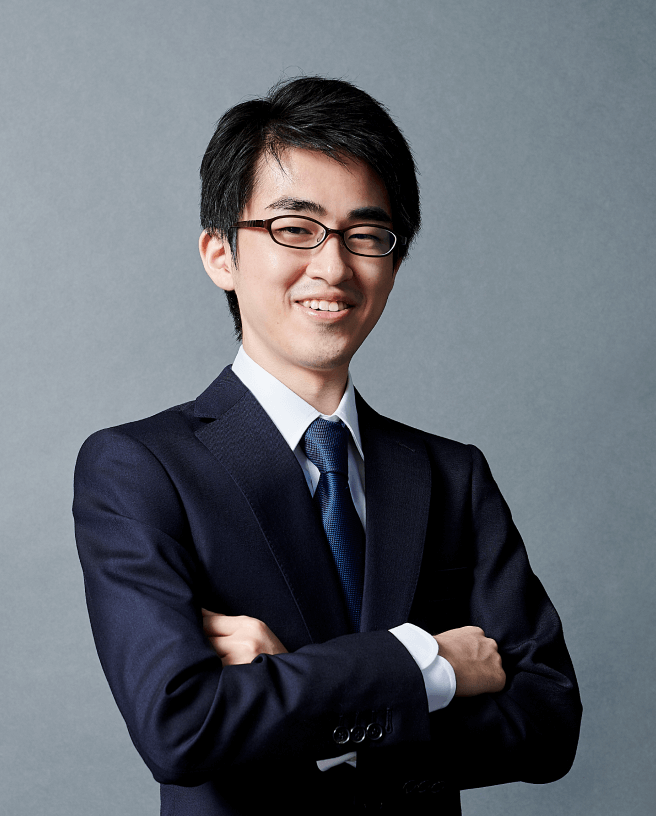
東京国際法律事務所
E-mail: yusuke.takeuchi
@tkilaw.com

