【JCAAセミナーリポート】新たな武器としての改正仲裁法およびJCAA規則に基づく暫定保全措置 ―シンガポールと香港における実務経験からの示唆を踏まえ
新たな武器としての改正仲裁法およびJCAA規則に基づく
暫定保全措置
―シンガポールと香港における実務経験からの示唆を踏まえ
東京国際法律事務所およびTKI (Singapore) LLPは、日本商事仲裁協会(JCAA)の主催、日本貿易振興機構(JETRO)の後援を受け、国際仲裁の中でも特に実務的かつ重要なテーマである「暫定保全措置」に関するセミナーを開催しました。
セミナータイトルを「新たな武器としての改正仲裁法およびJCAA規則に基づく暫定保全措置― シンガポールと香港における実務経験からの示唆を踏まえ」として、日本における最近の法改正、各国制度との比較、そして国際的な実務家および企業にとっての実務面における影響について議論が交わされました。
セミナーには両事務所から 山田広毅弁護士、アール・リベラ・ドレラ外国法弁護士、松本はるか弁護士 の3名が登壇し、クロスボーダー紛争解決の豊富な経験に基づく戦略的な見解を共有しました。
法改正:日本仲裁法の改正
今回のハイライトは、2023年に改正され2024年4月に施行された改正仲裁法でした。本改正は、2006年UNCITRAL模範法をモデルとして、日本の仲裁制度を国際標準に整合させることを目的としています。山田弁護士が説明した通り、特に大きな変化は、仲裁廷によって命じられる暫定保全措置が日本の裁判所により執行可能となった点です。 山田弁護士が説明した通り、特に大きな変化は、仲裁廷によって命じられる暫定保全措置が日本の裁判所により執行可能となった点です。
従来、日本の仲裁制度においては、暫定保全措置に法的拘束力を欠き、任意の履行に依存していたため、実効性が著しく制限されていました。改正後は、差止命令、資産凍結、証拠保全などの暫定保全措置命令を、日本の裁判所によって執行することが可能となりました。
暫定保全措置命令の例:
- 仲裁中に主要資産の海外移転を禁ずる命令
- 電子データの消去を防ぐための証拠保全命令
- いずれかの当事者が国内裁判所に提訴することによって仲裁手続を妨害することを防ぐ(提訴禁止差止命令)
今回の改正により、日本を仲裁地とする仲裁の実効性が飛躍的に高まり、特に緊急の保全が求められる場合や、仲裁判断前の場面での実用性が強化されました。
命令から執行へ:日本の裁判所の役割
また、改正仲裁法における暫定保全措置命令の執行手続についても解説されました。仲裁廷が発する暫定保全措置命令は、改正仲裁法第47条から第49条に基づき「執行認可決定」によって、裁判所による執行可能な決定となります。
当事者が暫定保全措置命令に違反した場合又は違反するおそれがあると認めるときは、日本の裁判所は「違反金支払命令」を発することができ、同命令を申し立てた当事者は(おそれがあるとされた違反が実際に生じた場合)資産の差押えなどの強制執行の申立てをすることができるようになりました。このような裁判所の関与により、仲裁廷による命令の履行可能性が飛躍的に向上し、仲裁手続の当事者による不誠実な行動への抑止力も強化されます。
また松本弁護士は、2022年に新設された東京地裁ビジネス・コートの役割を紹介しました。同ビジネス・コートは、国際商事仲裁関連の紛争に注力する国内初の専門組織であり、専門性を備えた裁判官や、バイリンガルの対応、オンライン審理、手続の透明性等のインフラを備え、仲裁を「支援するが干渉しない」バランスの取れた役割を担います。
特徴:
- 東京地裁における仲裁関連事件を一括処理
- ニューヨーク条約に準拠した解釈・判断を重視
- 外国人当事者や緊急案件に対して迅速かつ予測可能な審理を提供
仲裁廷と裁判所の連携により、日本は現代的かつ仲裁フレンドリーな法域であることを強く印象づけました。
海外からの教訓:シンガポールと香港の比較
JCAA規則に基づく仲裁人でもあるアール外国法弁護士は、シンガポールおよび香港における緊急仲裁制度について詳細な比較分析を行いました。
■ シンガポール(SIAC):
- 2016年SIAC規則:一方的申立による救済は不可。全当事者に通知が必要
- 2025年SIAC規則:PPO(暫定保全措置命令)により限定的に一方的申立による救済を許容
- シンガポール裁判所は、仲裁地が外国である場合も含め、緊急仲裁命令の執行を積極的に支持
■ 香港(HKIAC):
- HKIAC規則では依然として一方的申立による救済を認めず、当事者双方に意見表明の機会を付与することが必要
- 一方で、香港の裁判所は独自の判断で一方的申立による救済を認める裁量もあり
- 香港仲裁条例第22A条および第22B条により、仲裁地が香港外でも裁判所の許可があれば緊急救済を執行可能
- Company A v Company C 事件では、外国仲裁を補完する形で裁判所が暫定保全措置命令の執行を許可
両法域においては、国内裁判所が仲裁の暫定保全措置を強力に補完する存在となっており、裁判所による過度な介入を回避しつつ仲裁の実効性を支えています。アール外国法弁護士は、仲裁命令と裁判所の暫定保全措置命令のどちらを選ぶかを戦略的に考えるにあたり、事案の緊急性、資産の所在する場所、秘密保持の重要性といった検討要素が重要であると強調しました。
JCAA仲裁の優位性:戦略的・実務的メリット
本セミナーでは、日本企業だけでなく外国企業にとっても、JCAA規則に基づく仲裁の選択が有力であることも説明しました。JCAAは以下の特徴を備えています。
- コスト効率が高い
- 効率的な手続:3か月仲裁制度を最初に導入
- 緊急仲裁人制度は2014年から導入済みで、改正仲裁法により裁判所の執行力が加わったことで、象徴的ではなく実効的な暫定保全措置が可能に
実務シナリオ:理論と実務の橋渡し
本セミナーでは、改正仲裁法の下でJCAAの保全措置がどのように機能するかを示す実例も紹介されました。
- 日本企業(申立人)が、相手方が証拠データを破棄しようとしている情報を入手
- 申立人はJCAAに緊急仲裁人による暫定保全措置命令の申立
- 2営業日以内に緊急仲裁人が選任され、2週間以内に暫定保全措置命令発令
- 申立人は裁判所に執行等認可決定と違反金支払命令を申立て
- .申立人は、認可決定取得後、被申立人の別の日本企業に対する売掛金を差押え
この一連の流れは、迅速かつ執行可能で法域連携の整った新たな仲裁制度の実例として紹介されました。
結論:日本における仲裁の新章
本セミナーは、日本が国際仲裁の分野で果たす新たな役割に対する期待をもって締めくくられました。最近の法改正やJCAAによる制度的支援、仲裁を理解し支援する裁判所の体制により、日本はアジアの紛争解決市場において信頼でき、説得力のある環境を整備しました。
現在、日本は仲裁地として、法曹やインハウスロイヤー、クロスボーダー案件に関わる企業にとって、以下の通り非常に魅力的な条件を備えています。
- 執行可能な暫定保全措置という選択肢
- JCAAによる中立的かつ専門性の高い仲裁人の選任
- 東京地裁ビジネス・コートによる仲裁フレンドリーな司法支援
国際紛争が複雑化・広域化する中で、暫定保全措置はリスク管理のために不可欠な手段であり、日本は仲裁地として戦略的な選択肢となりつつあります。
※本記事の内容は、一般的な情報提供であり、具体的な法的又は税務アドバイスではありません。
ご質問などございましたら、ご遠慮なくご連絡ください。
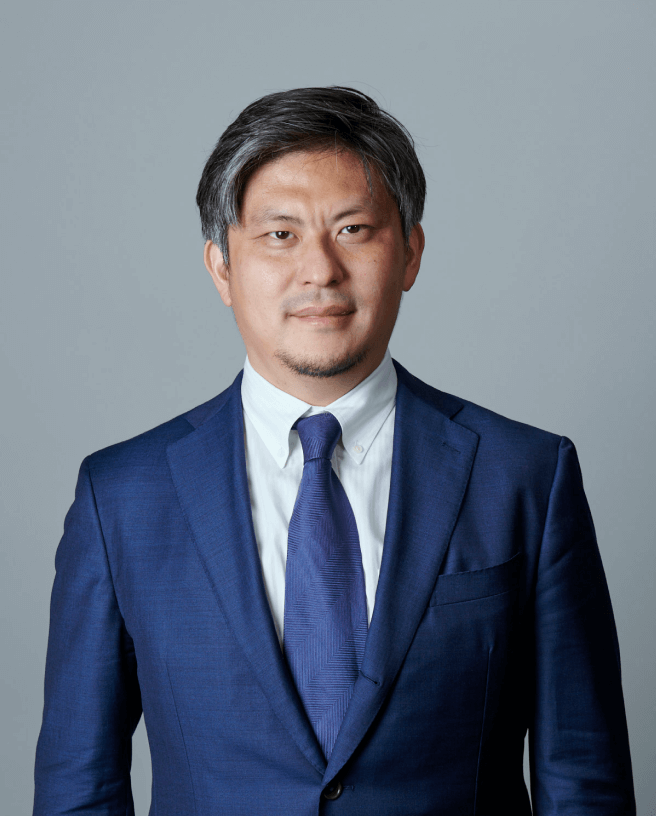
東京国際法律事務所/
TKI (Singapore) LLP
E-mail: koki.yamada@tkilaw.com

TKI (Singapore) LLP
E-mail: earl.dolera@tkilaw.com

東京国際法律事務所
E-mail: haruka.matsumoto@tkilaw.com

